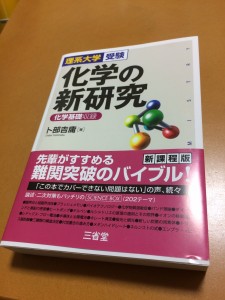「キャンベル生物学」という本を読んでいることは、本ブログやTwitterに何度か記述してるのだが、その本を読むたびに(特にミクロレベルの生命現象のところ)、化学の知識が求められる。
生物という「生存機械」の実体は、一連の代謝作用から成り立っていることなので、化学の知識が求められるのは当然だ。
私は、一応理系(数学)出身なので、受験までは化学を学んだはずなのだが、かなりの内容が忘却の彼方である。
特に有機化学は、高校時代からもっとも苦手な科目だった。
確か、駿台文庫の「必修化学」という本を買ったのだが、暗記するばかりで、全然面白くなかった覚えがある。
ただ、「キャンベル生物学」にも若干化学の説明が載っており、説明を読むと、「官能基」の性質など理屈を知れば面白いのではないかと感じたりもする。
そこで、忘却の彼方の化学の知識を少しでも呼び戻すために、化学の本を買おうと思いたつ。
近所の本屋の化学書コーナーに行って、物色していたのだが、余りにも専門分野に分かれており、「有機化学」、「無機化学」、「生化学」、「物理化学」など多数の本があり、しかも値段が高い。
かと言って、一般的な化学の本を見ると、中身が薄い。
そこで、受験参考書の化学書コーナーに行くと、化学の基礎知識を養え、なおかつ充実した内容の「化学の新研究」という本を発見した。
化学書コーナーにあった化学の解説本よりよっぽど詳しく記述されているようだ。パラパラと中身を見て、化学の基礎を学び直せる内容だと思ったので、早速購入した。
この内容を理解した後、必要であれば、高価な化学書を購入することにしよう。
ちなみに、「化学の新研究」の構成は以下のようになっている。
第1編 物質の構造
第1章 物質の構成と化学結合
1-1 物質の構成
1-2 原子とイオン
1-3 化学結合
第2章 物質量と化学反応式
1-4 原子量・分子量と物質量
1-5 化学反応の量的関係
第2編 物質の状態
第1章 物質の状態変化
2-1 粒子の熱運動と拡散
2-2 物質の三態と状態変化
2-3 液体の蒸気圧と沸騰
第2章 気体の性質
2-4 気体の性質
2-5 混合気体と蒸気圧
2-6 理想気体と実在気体
第3章 溶液の性質
2-7 溶解のしくみ
2-8 固体の溶解度
2-9 気体の溶解度
2-10 溶液の濃度
2-11 希薄溶液の性質
2-12 浸透圧
2-13 コロイド溶液
第3編 物質の変化
第1章 化学反応と熱
3-1 化学反応と熱
3-2 へスの法則と結合エネルギー
第2章 反応の速さと平衡
3-3 化学反応の速さ
3-4 化学平衡
第3章 酸と塩基
3-5 酸と塩基
3-6 中和反応と塩
第4章 酸化還元反応
3-7 酸化還元反応
3-8 電池と電気分解
第4編 無機物質の性質
第1章 非金属元素の性質
4-1 水素と希ガス
4-2 ハロゲンとその化合物
4-3 酸素・硫黄とその化合物
4-4 窒素・リンとその化合物
4-5 炭素・ケイ素とその化合物
4-6 気体の製法と性質
第2章 典型金属元素の性質
4-7 アルカリ金属とその化合物
4-8 アルカリ土類金属とその化合物
4-9 アルミニウムとその化合物
4-10 亜鉛・水銀とその化合物
4-11 スズ・鉛とその化合物
第3章 遷移元素の性質
4-12 遷移元素の特徴
4-13 錯イオンと錯塩
4-14 鉄とその化合物
4-15 銅とその化合物
4-16 銀とその化合物
4-17 クロム・マンガンとその化合物
4-18 金属イオンの分離・確認
第5編 有機物質の性質
第1章 有機化合物の特徴と分類
5-1 有機化合物の特徴
5-2 有機化合物の分類
5-3 有機化合物の構造決定
第2章 脂肪族炭化水素
5-4 アルカンとシクロアルカン
5-5 アルケン
5-6 アルキン
5-7 石油と天然ガスと石炭
第3章 脂肪族化合物
5-8 アルコールとエーテル
5-9 アルデヒドとケトン
5-10 カルボン酸
5-11 エステル
5-12 油脂
5-13 セッケンと合成洗剤
第4章 芳香族化合物
5-14 芳香族炭化水素
5-15 フェノール類
5-16 芳香族カルボン酸
5-17 芳香族アミン
5-18 有機化合物の分離
第6編 高分子化合物
第1章 天然高分子化合物
6-1 高分子化合物の分類と特徴
6-2 単糖類と二糖類
6-3 多糖類
6-4 アミノ酸
6-5 タンパク質
6-6 核酸
6-7 脂質
第2章 合成高分子化合物
6-8 合成繊維
6-9 合成樹脂
6-10 ゴム
6-11 イオン交換樹脂
6-12 機能性高分子
[amazonjs asin=”4385260923″ locale=”JP” title=”化学の新研究―理系大学受験”]